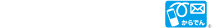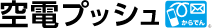さまざまなメッセージをやり取りするツールが出てきているにもかかわらず、スマホの標準アプリに搭載されていることから多彩な用途に使えるのがSMS(ショートメッセージサービス)です。シンプルなプライベートでのやり取りだけではなく、実はビジネスにおいても使い方次第で便利に利用することができます。そこでこの記事では、SMSの基本的な特徴や使い方とともに、パソコンからSMSを送信する方法や一斉送信の活用について詳しく紹介します。
- SMSは携帯電話やスマホに標準搭載された開封率・到達率の高いメッセージツールで、さまざまな場面で活用されている
- SMSをパソコンから送信することも可能で、複数人に一斉送信ができる、長文が簡単に入力できるといったメリットがある
- 法人がSMSをパソコンから送信するには、ビジネスに役立つ機能が搭載されたSMS送信サービスを利用するのがおすすめ
目次
- SMS(ショートメッセージサービス)とは?
- SMS(ショートメッセージサービス)にはどのような特徴がある?
- パソコンからSMSを送るメリット
- パソコンからSMSを送る際に気をつけるべき注意点
- 個人がパソコンを使ってSMSを送付する方法と手順
- 【法人向け】パソコンを使ってSMSを送信するにはSMS送信サービスがおすすめ
- SMS送信サービスを効果的に活用するポイント
- 【事例紹介】事前通知や緊急連絡から督促まで!SMSを顧客への連絡に活用しよう
- ビジネスで生かせる場が多い!SMSを顧客への連絡に活用しよう

SMS(ショートメッセージサービス)とは?
SMSはShort Message Service(ショートメッセージサービス)の略で、ショートメールとも呼ばれることもあります。携帯電話番号を宛先として、テキストでメッセージを送ることができるサービスです。国内の携帯キャリアでは1997年にサービスが開始されましたが、従来は携帯キャリアによって名称(ショートメール、Cメールなど)が異なっていました。さらに、同じ携帯キャリア同士でしかメッセージの送受信ができませんでした。しかし現在では、SMSに対応していれば携帯キャリアを超えてメッセージを送受信することができ、スマホ上ではチャット形式で表示されるようになっています。
SMS(ショートメッセージサービス)にはどのような特徴がある?
SMSはメールやLINEなどのほかのメッセージツールにはない特徴があり、さまざまな場面で活用されています。ここでは、SMSの5つの特徴を紹介します。
SMSは携帯電話・スマートフォンに標準搭載されている
SMSの最大の特徴は、携帯電話・スマートフォンの標準アプリとして搭載されているため、誰でも容易に使える点です。メッセージの送受信のため、わざわざ特別なアプリをインストールしたり、アカウントを登録してもらったりする必要がありません。
また、受信するとポップアップ画面に表示されるので届いた際に気付きやすいという特徴もあります。
開封率・到達率が高い
SMSの利点は着眼率が高く、結果として開封率も非常に高くなる点にあります。
またSMSは通知記録として残るため、届いた瞬間にすぐに確認しなくても、通知記録からSMSの受信に気づきます。
顧客に各種情報を届けるポピュラーなツールにメールがあります。しかし、メールアドレスは携帯電話番号に比べると発行や変更が容易で、メインとサブなど複数のアドレスを使い分ける人もいます。
そのため、顧客に確実に見てもらいたいなら、メールよりもSMSが優れているといえるでしょう。
関連記事:SMSとは何か?各種メッセージサービスとの比較で完全理解
携帯電話番号は変更されることが少なく、本人認証にも活用
メールアドレスの場合はパスワード忘れや迷惑メールが増えて変更したり、複数所持することがあります。そのため、メールアドレスを変更しWebサービスの登録情報はそのままにしておくケースもよくあり、メッセージが届かない原因の一つとなっています。また、迷惑メール対策を施しているケースでは届いたメールが迷惑フォルダに振り分けられ、送付してもそもそもユーザーの目に触れない可能性もあります。
宛先が携帯電話番号のSMSでは、インターネットを経由してメッセージのやり取りを行うのではなく、携帯電話の回線が使われます。携帯電話番号はよほどの理由でもない限り、ほとんど変更されることがありません。ナンバーポータビリティ(MNP)の制度が整っていることもあり、携帯キャリアを変更してもそのまま番号を引き継いで使うことが多くなっているため、送信エラーを少なくすることができます。
また、携帯電話番号は所有者と紐づいているため、なりすましを防ぎユーザーを特定することが可能です。そのため、さまざまなサービスやアプリをダウンロード・ログインする際の本人認証としてSMS認証が多く使われるようになっています。
文字数制限がある
SMSはメールやLINEなどのほかのメッセージツールと違い、送受信できる文字数に制限があります。SMSサービス開始当初の最大文字数は全角70文字まででしたが、現在ではその制限が拡張され、全角最大670文字までの送信が可能になっています。
もし670文字以上の文章を送信する場合はエラーになる、もしくは分割されて送信されるため注意が必要です。また、古いモデルの携帯を使用している場合は制限が異なる場合があるため確認しましょう。
関連記事:SMSの文字数制限とは?活用例やサービスを選ぶポイントも紹介
コストを抑えることができる
SMSを送信する費用は1通あたり数円~数十円と非常に低価格です。ハガキやダイレクトメールを郵送するよりも安いため、コストを抑えるためにSMSで代用するケースも増えています。電話も通話料がかかるうえ、つながらなかった場合は何度もかけ直さなければなりません。
一方でSMSは受信者の開封率が高く、都合のよい時にテキストの内容を確認することが可能なため、費用だけでなく手間や時間も削減できます。また、SMSの受信者には費用が発生しないため、お客様に送信する場合でも負担はかかりません。
パソコンからSMSを送るメリット
携帯電話番号を用いてやりとりを行うSMSですが、SMS送信サービスを活用することで、パソコンからメッセージを送信することもできます。ビジネスにSMSを活用している企業では、パソコンからSMSを送ることが多いです。ここでは、パソコンからSMSを送るメリットについて解説します。
複数人に一斉送信ができる
携帯電話やスマートフォンからSMSを送る場合、宛先の電話番号を入力して1件ずつ送信しなければなりません。複数人に同じ内容のメッセージを送る場合は非常に手間がかかり、宛先の入力ミスが発生する可能性も高くなります。
一方でパソコンからSMSを送る場合は、一斉送信に対応したSMS送信サービスを利用することで一度に複数人に対して同時にメッセージを送信できます。今までSMS送信に費やしていた時間や手間を大幅に削減できるでしょう。顧客に対するイベントやキャンペーンのお知らせなど、大量配信が必要な場合にも最適です。
長文の入力が簡単にできる
パソコンからSMSを送る場合、長文の入力が簡単かつ効率的に行えます。携帯電話やスマートフォンから長文のメッセージを入力するのは難しく、時間のかかる作業です。しかしパソコンのキーボードからであればスムーズに入力できるため、大きなメリットと言えます。
もし今までパソコンで文章を作成してからスマートフォンに送り、スマートフォンからSMSを送信していた場合は、パソコンから直接SMSを送信することで手間を省けます。
パソコンからSMSを送る際に気をつけるべき注意点

SMSは携帯電話番号を宛先にして送受信することから、SMS送信サービスを利用すれば、パソコンから一斉・大量にSMSを送ることが出来ます。 ただし、SMSはシンプルなメッセージサービスなので送る際にはいくつか注意点があります。ここでは、SMSを送信する際に気をつけておくべきポイントについて詳しく説明します。
(関連記事:SMS(ショートメッセージサービス)の送り方と4つの注意点)
本文内には必ず送信者名を記載する
SMSは携帯電話番号で送受信することから、送信元としては基本的に電話番号が表示されます。家族や友人など、ユーザー側の携帯電話のアドレス帳に登録されている番号はメッセージが届くと登録された名称で表示されるため、誰からのものか一目でわかります。しかし、登録されていない場合は番号しか表示されません。
番号の表示だけしかされなければ受け取ったユーザーはすぐに送付元を把握することができず、迷惑メールとの区別がつかない可能性もあります。せっかくポップアップ画面に通知が表示されても、送信元がはっきりしないメッセージは開封率が下がることも考えられます。そこで大切なのは送信者名が本文に記載されていることです。企業が利用する際は、社名などを本文に明記することで心当たりのないメッセージとして開封されなかったり、削除されたりすることを防ぐことができます。
また、不明な番号をインターネットで検索する場合もあるため、SMSの送信元番号をWebサイト上へ明記し顧客に案内することを推奨します。
メッセージはできるだけ70文字以内にする
SMSはそもそも短文をやり取りするサービスのため、従来は1回に送信できる標準文字数は全角70文字以内が一般的でした。2019年には大手携帯キャリアを中心に最大で全角670文字まで送信できるようにサービスが拡大されています。ただし、670文字のメッセージをやり取りするためには、受信側も670文字のSMSを受信できる機種であることが前提です。そのため、初めての相手に送信するメッセージは全角70文字以内におさめておいたほうが無難です。
(関連記事:特許取得!長文メッセージ送信機能をアップデート~長文SMS送信時の問題を解消!~)
個人がパソコンを使ってSMSを送付する方法と手順
個人がパソコンを使ってSMSのメッセージを送付するときは、スマートフォンとパソコンを連携する必要があります。iPhoneとAndroidで方法が異なりますので、実際にパソコンを使ってSMSを送信する方法を紹介していきます。
【重要】SMSが送信できるスマートフォンとパソコンの連携が必要
SMSは携帯電話の回線を使ってメッセージをやり取りする方法であるため、ガラケーやスマートフォンからは直接メッセージを送信することができます。しかし、パソコンは携帯電話回線と直接つながっているわけではないため、そのままではメッセージの送信はできません。パソコンを使ってSMSを送付するためには、SMSが送信できるスマートフォンとパソコンを連携させることが必要です。
iPhone経由で、パソコンからSMSの送受信をするには、Macのメッセージ
iPhoneを介してパソコンからSMSを送信する場合は、Macのメッセージ送信機能を使います。
- Macのメッセージで、使用するiPhoneと同一のAppleIDでサインインする
- iPhoneの設定で、メッセージ>SMS/MMSから転送使用するMacをオンにする
※ 確認コードがMac側に表示されますので、iPhoneに入力
このようにMacとiPhoneを連携することで、MacのメッセージからiPhoneを経由してSMS/MMSを送信することが出来ます。
(参考記事:iPhone から iPad、iPod touch、Mac に SMS/MMS テキストメッセージを転送する方法)
現段階で、Windowsのパソコンから、iPhone経由でSMSの送受信方法は確認出来ませんでした。
Android経由で、パソコンからSMSを送受信するには、Chromeブラウザ
Android端末にはもともとSMSが使えるアプリがプリインストールされていますが、それとは別にGoogleのメッセージアプリを利用してSMSを送付することが可能です。Googleが提供しているAndroidメッセージにはPC版もあり、パソコンを使ってメッセージの作成や送受信を行うことができます。PC版とはいえ、モバイルアプリを使用する場合と同様にAndroid端末の電話回線が使用されるため、パソコンでAndroidアプリを使用する際はスマートフォンとパソコンを連携させておくことが必要です。
パソコンからPC版メッセージにアクセスすると、固有のQRコードが割り当てられます。スマートフォン側でメッセージアプリを開き、その他アイコン(3点リーダー)をタップして表示される「ウェブ版Androidメッセージ」をさらにタップします。「PC版を開く」から「QRコードをスキャン」をタップしてパソコンに表示されているQRコードを読み込むと、パソコンにPC版Androidメッセージが表示されてペアリングの設定は完了です。なお、PC版Androidメッセージを利用できるブラウザはChromeまたはMozilla Firefox、Safari、Microsoft Edgeのみで、Internet Explorerは利用できません。
(参考記事:パソコンでメッセージを確認する - Messages ヘルプ)
【法人向け】パソコンを使ってSMSを送信するにはSMS送信サービスがおすすめ
スマートフォンなど、一般のモバイル端末からは、SMSは個別にしか送信できないため、企業や法人が多数の顧客向けにメッセージを送信するには向いていません。しかも送信上限があり、1日に200通しか送信できないのもネックです。
しかし、SMS送信サービスを利用すれば、送信数の制限はなくなります。パソコンからWeb管理画面を操作して、SMSを多数の顧客向けに個別もしくは一斉に送信することが可能です。
SMS送信サービスとは、ビジネスでSMSを利用する場合に役立つ便利な機能が搭載された法人向けサービスのことです。個人でSMSを送信するよりも送信性能が高いため到達率が上がったり、セキュリティ対策が強化できたりするなど、さまざまなメリットがあります。法人がパソコンを使ってSMSを送信する場合、確実で安心な配信を実現するためにはSMS送信サービスの利用が最適です。
SMSの一斉送信については、詳しくは以下のページをご覧ください。
関連記事:SMSを一斉送信するには?メリットとサービスの選び方
SMS送信サービスを効果的に活用するポイント

企業や法人がSMSを使ってメッセージの送信を行う場合は、最適なSMS送信サービスを選定することが必要です。
ここで、法人がショートメッセージの一斉送信を活用するにあたって、留意したいポイントについて詳しく解説します。
国内携帯キャリアと連携しているサービスを選ぶことがポイント
まず、一度に多くのユーザーに向けてメッセージを発信したい場合は、パソコンを使ってSMSを一斉送信できる専用の送信サービスを利用することがポイントです。SMSの一斉送信を専門にしているサービスでは、簡単にメッセージを送信できるため、電話や郵送で顧客へ連絡を取っていた場合は大幅な効率化が見込めます。
ただし、一斉送信で大量にメッセージを送信することになれば、送信先の受信状況を個別に把握することは難しくなります。たとえばURL付きのメッセージを送った場合、国際回線を利用してSMSを送付すると、迷惑メールとして中継事業者や携帯キャリアに判断されてメッセージが届かない可能性もあります。悪質な架空請求などのメッセージを受け取らないための対策として、国際回線を使って送付されるメールに対してブロックをかけていることも珍しくありません。確実にSMSを届けるためには、国内携帯キャリアと連携しているSMS送信サービスを利用することがポイントです。
送信性能の高いサービスを選ぶ
SMSを着実に顧客の元に届けるため、送信性能の高いSMS送信サービスを選択しましょう。SMSの送信性能とは、たとえば以下のような事項を元に判断します。
- 送信の処理能力
- 到達率
- 誤送信・未達回避
まず、送信できる処理性能を見ます。多くの顧客にSMSを一斉送信しようにも、そもそも自社の顧客の数を下回る数しか同時送信できないサービスだと利用しにくいでしょう。
次に、基本的な到達率を確認しましょう。100%に近いことが望ましいです。
また、誤送信や未送信を回避できる機能があるとベターです。例えば、携帯番号の契約者変更の判定や、端末の電源オフ、圏外の場合の再送機能があれば、着実に顧客にメッセージを届けられます。
広告宣伝のSMS一斉送信には同意を得る必要がある
パソコンで広告宣伝のSMSを一斉送信するときは、特定電子メール法(特電法)に注意する必要もあります。特定電子メール法は正式名称を「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といい、2002年から施行されている迷惑メールの送信を規制する法律です。施行後2007年には架空アドレス宛てにメールを送信することが禁止されたほか、広告宣伝メールの配信に関しても範囲が拡大されています。2008年にはさらに法律が改正され、「オプトイン規制」も導入されました。
オプトイン規制とは、あらかじめ同意を得た人に対してだけメールの送信ができるというもので、SMSの配信にも適用されます。この規制に違反するメールを送付した場合は罰則があるため、SMSの一斉配信を行う場合は必ず送信の同意を取ることが必要です。また、送信者側にはメール本文に送信者の名称、および受信拒否の通知を受けるためのURLや連絡先を入れるなどいくつか表示義務があります。SMSを一斉送信できる方法でメッセージを送るときは、特定電子メール法に抵触しない形でメールを送るよう注意しなければなりません。
(関連記事:SMS導入担当者が必ず理解しておきたい3つの法律)
本人認証など自動送信の機能はAPIの連携が必要となる
サービスやアプリのログイン時のセキュリティ対策に、多くのサービス事業者が、多要素認証を活用しており、SMS認証もその一つです。自社サービスの提供において、本人確認の手段にSMS認証を取り入れる場合、いくつか注意が必要です。
SMS認証の円滑な運用のため、SMS送信の自動化が欠かせません。つまり、自社システムとSMS送信プロセスの連携が必要になります。一般的な方法として、自社の認証システムとSMS配信サービスが提供するAPIを接続、連携します。
注意したい点として、そもそも自社システムがAPIに対応しているのか、どういった仕様のAPIが提供されているかなどを見極めなくてはならないことがあげられます。
関連記事:SMSのAPI連携のメリットとは?自動送信への活用と導入の流れ
定期的に効果測定を行う
SMS送信サービスを利用すると、簡単に大量のSMSを送信できるようになります。しかし、ただ闇雲に送るだけでは料金ばかりかかってしまい本来の目的を果たせない可能性があります。そのため、必ずSMS送信の目的や目標を設定したうえで、定期的に達成できているか効果測定を行うことが大切です。
送信するメッセージの内容や送るタイミングから得られた結果を分析し、より効果的なSMS送信ができるよう改善します。これによりコストパフォーマンスを向上させることが可能です。目的を達成するために、意味のあるSMS配信を行うことを意識しましょう。
【事例紹介】事前通知や緊急連絡から督促まで!SMSを顧客への連絡に活用しよう
SMS送信は即時性、また着実な到達性が評価されています。こういったSMSの特徴を生かし、企業はどのようにSMSを活用しているのでしょうか。
ここでは弊社のSMS送信サービス「空電プッシュ」をご利用された3社のSMSの活用事例を紹介します。
緊急連絡や決済・督促通知など、重要な顧客連絡にSMSが活用されている例や、顧客の声を効率的に集めるためにSMSを活用している事例を紹介します。
緊急の連絡や予約のリマインド
国内で小型ジェット機を運航する、アイベックスエアラインズ株式会社では、新型コロナウイルスの感染拡大による運行スケジュールの変更にともなう事務負担の軽減のため、SMS送信サービスを導入しました。
従前から旅客機の欠航や遅延の連絡事務に課題があり、自社システムの仕様でフライト間近にならないと顧客のメールに連絡を送れず、また開封されない場合も散見され、確実を期すには電話連絡の手段しかありませんでした。また、欠航・遅延時の顧客関係事務は手間がかかり、フライト情報の連絡のみならず、払い戻しや別便の手配など、一人ひとりに説明が必要でした。
そこに感染症の拡大が起こり、電話スタッフの確保も困難に。SMS送信サービス「空電プッシュ」を採用した後は、連絡事務に必要な人員が従前の5~6名から1名体制での運用が可能になったほか、問い合わせやクレームも大幅に減ったとのことです。
決済通知や催促
法人、および個人向けにレンタル携帯サービスを展開している、株式会社アーラリンクでは、従来から料金請求の連絡にSMSを活用していました。しかし、担当者個人の携帯電話を利用してSMSを送信していたため、とても非効率的でした。事業の成長にともない、SMSの一斉送信サービスの必要性が増していきました。
SMS送信サービス「空電プッシュ」を導入した理由は、100%近い到達率の高さ、使い勝手の良さ、納得できる価格設定でした。
SMS送信サービスに慣れた今は、支払いタイミングと受領連絡のズレによる顧客の不安払拭のため、システムのAPI連携機能によるタイムリーなSMS送信が実施されています。今後は開封状況に応じたフォローの仕組み構築に取り組みたいとのことです。
アンケートの回収
SMSの一斉送信は、情報提供に使われることが多いですが、顧客の声を収集する手段として使われてもいます。
明治安田生命保険相互会社では顧客満足度向上を目的に、SMS送信サービスを導入しました。現在は「コールセンター対応」「訪問サービス活動」に関する顧客アンケートの媒体にSMSを活用しています。SMS送信サービス選定で重視したのはセキュリティ面でした。空電プッシュはその点、信頼感が持てると感じられたそうです。
従来は郵送での顧客アンケートを実施していましたが、サービスを受けてからの時間差もあり、効果的な分析や改善活動につなげにくい状況がありました。SMS送信サービス導入後はアンケート回収率が大きく向上、サービス品質改善に役立てたり、社内全体の士気向上にもつながっているとのことです。
ビジネスで生かせる場が多い!SMSを顧客への連絡に活用しよう

新しいメッセージツールが次々出てくるなかで、依然としてSMSが使われ続けています。スマートフォン単体で送受信するだけではなく、パソコンで多くの顧客に一斉送信できる方法も確立され、ビジネスのさまざまな場面で活用できるようになりました。SMSは埋もれてしまうリスクが少なく、見てもらえる確率が高いです。今後、顧客との連絡手段の一つとして、SMSを取り入れてみてはいかがでしょうか。
NTTコム オンラインのSMS送信サービス「空電プッシュ」は高い到達率とセキュリティ、使い勝手の良さが特徴です。ぜひ一度ご検討ください。