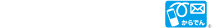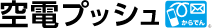SMSは、携帯電話番号宛にメッセージを送信できる携帯電話・スマートフォンの標準機能です。チラシやダイレクトメール(DM)といった他の販促手段よりも、コストを抑えて幅広い層にアプローチできるため、マーケティングや販促に導入する企業も増えています。
本記事では、販促ツールとしてSMSを活用すべき理由や主な活用事例などについて解説します。
実際にSMS販促によって効果が得られた事例や、SMS販促を導入する上での注意点も紹介するので、ビジネスにおけるSMSの有効活用方法について知りたい方はぜひご覧ください。
目次
- SMSが販促手段として注目される理由
- SMS以外の販促方法
- SMSの販促への活用例
- SMSを使った販促の事例
- SMSを販促に利用する際の注意点
- SMSを販促の活用するならSMS送信サービスを利用しよう

SMSが販促手段として注目される理由

顧客とのコミュニケーションやユーザー認証の手段として、多くの企業がSMS(ショートメッセージサービス)を取り入れています。ここでは、SMSが企業の販促手段として注目される主な4つの理由について解説します。
携帯電話番号でやりとり可能
SMSは、携帯電話番号を用いてメッセージを送受信できる機能です。総務省のデータによると、令和3年度の携帯電話の契約数は約2億292万件で、前期比は1.5%増でした。
2021年度の日本の総人口が約1億2,550万人であり、単純計算で1人1台以上は携帯電話を所有していることになるため、多くの人にリーチできる可能性が高いでしょう。
到達率・開封率が高い
SMSの特徴として、到達率や開封率が高いことが挙げられます。近年のMNP(携帯電話番号ポータビリティ)の浸透に伴い、機種変更後も同じ電話番号を引き継ぐ人が増えています。そのため、本人に連絡できる確率が高く、高い到達率を維持しています。
また、SMSはテキストメッセージのみのシンプルな機能である分、視認性が高い点が特徴です。デフォルトでポップアップ通知設定があるため、他のメッセージに埋もれにくい傾向があります。さらに、ガラケーやスマホなど機種に問わず携帯電話に標準搭載されており、アプリのインストール不要で使うことができます。
リアルタイムに情報を届けることができる
SMSでは、リアルタイムに情報を届けることが可能です。ダイレクトメール(DM)やチラシの場合、企画から印刷、郵送といった手順を踏むため、すぐに伝えたい有益な情報も届く頃には時間が経っています。LINEやメルマガは時間はかからなくても、活用している企業が多いため、他の宣伝広告に埋もれて見てもらえない可能性もあるでしょう。
その点、SMSはリアルタイムで配信できるため、急に決まったイベントや臨時休業といった緊急性の高いお知らせも、必要なタイミングに届けられます。
送信コストが低い
SMSの受信は無料ですが、携帯電話からの送信には1通ごとに料金がかかります。文字数によって金額は変わりますが、1通あたり約3~33円ほどが相場です。(法人向けSMS送信サービスの単価とは異なります)
ハガキや封書を送るには1通63円以上、チラシは印刷代や配布時の人件費もかかるため、SMSの方が割安です。そのため、大量に配信したい場合にも利用しやすいでしょう。
ただし、携帯電話から1通ずつ販促やプロモーションのSMSを送ることは非効率的です。企業の販促等でSMSを利用する場合には、法人向けのSMS送信サービスを利用するとよいでしょう。
SMS以外の販促方法

企業が使用する販促方法には、SMS以外にもチラシやダイレクトメール(DM)、LINEなどのメッセージアプリ、メールマガジンなどがあります。販促の効果を最大限得るためには、自社に最適な販促方法を選ぶことが重要です。各手段のメリット・デメリットについてここで押さえておきましょう。
ビラ・チラシ
ポスティングや新聞折り込みで使われるビラやチラシは、インターネットが浸透する前から広く用いられてきた定番の販促方法です。
特定地域を中心とした大量配布に適しており、主婦や高齢者などインターネットの利用頻度が少ない層に情報を届けやすい方法です。手元に直接届けられるため、受け取り側は気になるものを保管して、好きなタイミングで読み返すことができます。
一方で、他の書類や広告に埋もれやすい、制作や配布にコストがかかるといったデメリットもあります。新聞購読者や地域住民など対象が限定的でありつつも、ターゲット層を細かく指定することが難しく、関係のない人が受け取った際にクレームにつながる可能性も考えられます。
ダイレクトメール(DM)
ダイレクトメール(DM)は、顧客の元へはがきや封書を直接送付する方法です。すでに購入や来店があった顧客への送付が中心で、エリアや性別といったターゲットを絞り込んで送付できます。チラシやカタログなどさまざまな形式で情報を届けられる上、高い開封率が期待できます。
ただ、デメリットとして企画から発送まで時間がかかりやすい点や、印刷代や郵送費用などコストが高くなる点が挙げられます。鮮度の高い情報を届ける手段としては不向きです。
メッセージアプリ
LINEをはじめとするメッセージアプリも、企業の販促手段として広く使われています。企業の公式アカウントを取得して、友だち登録してくれたユーザーに対して一斉配信することが可能です。
LINEの資料データによると、2020年9月末時点で、LINEの国内月間利用者は8,600万人で、日本の全人口の約68%が利用している計算です。プラットフォーム自体が大きいがゆえに、多くのユーザーに向けた効率的かつ効果的な訴求が実現します。また、1対1のトークによる関係性の構築、リアルタイムの情報発信といった点でメリットがあります。
ただ、個人のコミュニケーションツールという位置付けが強く、ビジネスユースが敬遠されがちなため、友だち登録をしてもらえるまで効果が期待できない可能性があります。また、アプリを利用しないガラケーユーザーへのアプローチが難しい点もデメリットです。
メールマガジン
メールマガジンは、メールで一斉配信する情報発信方法のことで、多数の相手に対してリアルタイムに配信できる点に強みがあります。ステップメールや定期配信が簡単に行えて、ユーザーとの関係構築にも効果的です。メール配信システムを使う場合は利用料が発生するものの、通信料自体は安く、コストを抑えられます。
一方で、他のメールに埋もれて確認や開封がされない、メール数が多いことで迷惑メールに登録されるといったリスクがあります。また、特定電子メール保護法の違反にも注意が必要です。
SMSの販促への活用例

ここからは、SMSの販促活用例について詳しく解説します。SMSを先述した販促方法の代わりに導入して、さらなる効果を得ることも可能です。SMSの活用アイデアとして参考にしてください。
キャンペーンやセールイベントの告知
SMSをキャンペーンやセールイベントの告知に活用することが可能です。開封率の高いSMSを使って、新規キャンペーンや期間限定のセールなどをお知らせすることで、認知してもらえる確率がアップします。また、顧客接点の強化にも役立ちます。
リアルタイム性が高い点を活かし、段階的に情報を届けると効果的です。例えば、セール前に告知文を送り、セール中には開催中として再度お知らせする、セール終盤には「終了まであと◯日」といったようにタイミングによって異なる通知を入れることで、集客率の向上が期待できます。
クーポンの送付
クーポンの送付にもSMSが有用です。割引や無料プレゼントといったクーポンは、顧客の購買行動のきっかけとなる可能性が高く、SMS上での配布によりWebサイトへの誘導や来店数の向上といった効果が期待できます。
ただ、SMSは文字数制限があるので、できるだけ端的かつ購買意欲に結びつくような文章を意識しましょう。
来店後のアフターフォロー
来店や購入のあったユーザーに対し、後日アフターフォローをSMSで送信します。短いメッセージであっても、感謝の意図を改めて伝えることで顧客の印象がアップします。また、顧客接点が増えるため、顧客との信頼関係を深められるでしょう。
ここで次回の来店や購入時に使える特典クーポンを配布すれば、リピーター獲得にもつながります。
アンケート調査
SMSはユーザーへの到達率が高いため、アンケート調査への参加を依頼する際にも役立ちます。商品やブランド、企業に対するユーザーからの意見は、顧客満足度や顧客体験向上において貴重な情報です。
SMSでアンケートフォームのURLを送る方法であれば、店舗やWebサイトを使った感想や商品・サービスのレビューなどの情報を、効率的に収集できます。
休眠顧客へのアプローチ
長い間訪問や購入がない顧客のことを休眠顧客と呼びます。休眠顧客へのアプローチにも、変更される可能性の低いSMSが有用です。SMSを通してコンタクトを行えば、ブランドや商品・サービスについて思い出してもらい、購買意欲を高めることができます。
また、DMと組み合わせた活用も効果的です。例えば、DMを先に送付しておいて、数日から1週間の期間に到着確認のSMSを送ることで、接点が増えるため、認知度や潜在ニーズの刺激につながります。
SMSを使った販促の事例
SMSを使った販促事例として、青森マツダでの活用例を紹介します。青森マツダでは、新車情報や在庫状況の配信、イベント告知のプロモーションにSMS送信サービスによるSMS販促を導入し、WebサイトのPV数の増加や業務負担の軽減といった効果を実現しています。
それまでは郵送DMを中心に利用していたものの、到達率や開封率が不明な上、最新情報を旬なタイミングで届けることが難しいなどの課題がありました。そこで、紙のDMより高い開封率が見込めるSMSを取り入れ、閲覧数を増やすために、SMS送信サービスの導入に至ったと言います。
また、300通ほどのDM送付にかかっていた人員コストの負担も、SMSへの切り替えによって約2割前後まで削減されています。具体的には、月1〜2回の頻度で1回あたり約4,200~4,300通を送信しています。実際に、店舗での中古車の独自展示会やメーカー協賛イベントにも、SMSを見て来場する人が増えたことが確認されています。
青森マツダでのSMS販促の導入から運用まで、詳しくは下記記事をご覧ください。
SMSを販促に利用する際の注意点
SMSは活用方法が幅広く、多くのメリットがありますが、導入にあたって確認すべきポイントもあります。ここではSMSを販促に利用する際の注意点について解説します。法律も関係するため、事前にチェックしましょう。
文字数制限がある
SMSには文字数制限があり、原則として最大全角670文字までしか送信できません。また、携帯電話の種類によっては全角70文字しか受信できず、超えた場合は分割されて表示されます。
そのため、メルマガやダイレクトメール(DM)のように多くの情報を1度に届けられず、内容次第では効果がさほど得られない可能性があります。
画像や動画ファイルは添付できない
SMSはあくまでも短い文章をやり取りできる機能であり、画像や動画、PDFファイルなどテキストメッセージ以外のものは送信できない点にも注意が必要です。
対策としては、概要や言いたいことを簡潔にテキストでまとめ、詳細はWebサイトへ誘導することで画像や動画にアクセスしてもらいましょう。
関連記事:SMSで画像や写真を送るには? 送信方法を詳しく解説
特定電子メール法を遵守する必要がある
メールマガジンと同じく、SMSで広告宣伝目的の内容を送る場合は「特定電子メール保護法」を遵守する必要があります。特定電子メール法とは、迷惑メール対策を含むユーザーの快適なネット環境を守るための法律です。
企業が販促案内を送信する際には、顧客から事前に同意を得る必要があること、またメッセージが不要な場合には顧客がすぐ配信停止できるよう配慮すること、などが定められています。
必ずユーザーから同意を得た上でメッセージを配信することや、メッセージ配信を解除できる旨の表示、連絡先情報の記載を徹底しましょう。
SMSを販促の活用するならSMS送信サービスを利用しよう
電話番号宛にメッセージを送信できるSMSは、開封率や到達率が高く、他の販促方法では難しかったターゲット層へのアプローチを促します。キャンペーンやクーポンの配布、フォローメッセージといった販促目的でSMSを活用する際には、特定電子メール法に留意し、自社に適した運用を行うことが大切です。
NTTコム オンラインが提供する空電プッシュは、PCから個別・一斉にSMSを送信できるサービスです。メッセージの一斉配信や予約送信、開封確認率データ収集や顧客管理システムとの連携など、多彩な機能が使えます。SMS送信導入をお考えの方はぜひご検討ください。