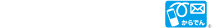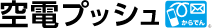ECサイトを運営していると、「ユーザーが買い物カゴに商品を入れているのに、購入まで進まないケースが多い」という事態に陥ることがあります。これをカゴ落ちといい、ECサイトを運営する事業者にとってはなるべく発生させたくないものです。
カゴ落ちにはさまざまな原因があるため、自社のECサイトでカゴ落ちが起きている原因を特定して適切な対策を取る必要があります。この記事ではカゴ落ちが起きる原因と対策、SMSを活用したカゴ落ち対策を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- カゴ落ちとは、ECサイトでユーザーが商品を買い物かごに入れたまま、購入せずに離脱してしまった状態のこと
- カゴ落ちが起きる原因には、「想定外の費用がかかる」「購入完了までのプロセスが長い」「配送に時間がかかる」「支払い方法の選択肢が少ない」などがある
- カゴ落ちを防ぐには、「送料や手数料を下げる」「会員登録を不要にする」「配送オプションを増やす」「カゴ落ちをリマインドする」といった対策が効果的
目次
- カゴ落ちの意味とは?
- カゴ落ちはどれくらい生じている?
- カゴ落ちが起きる代表的な10の原因
- カゴ落ちを防ぐ9つの対策
- カゴ落ちのリマインドにはSMSがおすすめ
- SMSによるカゴ落ちのリマインド例
- カゴ落ちをSMSで回避しよう

カゴ落ちの意味とは?
カゴ落ちとは、ECサイトでユーザーが商品を買い物カゴやカートに入れたものの、購入せずにサイトを離脱してしまったことを意味する用語です。カゴ落ちは販売機会の損失を意味し、多くのECサイトで課題として認識されています。
一度は商品をカゴに入れているので、ユーザーには少なからず購買意欲があったと考えられるでしょう。そのため、カゴ落ちの原因を特定して解消することで、売上につなげられる可能性があります。
カゴ落ちはどれくらい生じている?

どのくらいのカゴ落ちが発生しているのかは、以下の計算式で求められます。
・カゴ落ち率(%):(1-購入完了数÷作成されたカート数)×100
例えば200個のカートが作成され、そのうち80個のカートが購入完了となった場合のカゴ落ち率は、以下のとおりです。
・(1-80÷200)×100=60%
2021年から2022年にかけて株式会社イー・エージェンシーが実施した調査では平均カゴ落ち率は64.7%でした。また、カゴ落ちによる機会損失の金額を算出したところ、平均して売上の2倍にまでのぼるという結果も出ています。
このようにカゴ落ちによる損失は大きく、ECサイトを運営するうえで無視できない課題です。
カゴ落ちが起きる代表的な10の原因
カゴ落ちの発生を防ぐには、まず原因を特定する必要があります。カゴ落ちはさまざまな原因で発生するため、まずは代表的なものを把握しておきましょう。
カゴ落ちが起きる代表的な10の原因を紹介しますので、自社のECサイトで想定されるものがないかチェックしてみてください。
送料や手数料など想定していない追加の費用がかかる
ユーザーは商品ページに記載されている販売価格を見て購入を決めます。商品ページで送料や手数料、税込価格などが確認しづらい場合、ユーザーは買い物カゴの画面で想定外の追加費用を目にすることになります。
トータルの金額は同じでも、はじめから追加の費用を想定していた場合と比べて「想定していたより高い」と感じるほうが購買意欲が低下するため、注意が必要です。
購入金額の合計が決済前までわからない
購入金額の合計が決済前までわからないのも、ユーザーが「想定していたより高い」と感じる原因になります。複数の商品を購入する場合、それぞれの商品の金額は商品ページで確認できても、合計金額は買い物カゴを表示させなければ確認できません。
いざ購入しようと買い物カゴを見たときに合計金額が想定より高いと、購入せずにサイトを離れてしまう人もいます。
購入が完了するまでのプロセスが長い
ECサイトで商品を購入するには、住所や氏名、決済方法などの情報を入力しなければなりません。このような購入完了までのプロセスが長く手間がかかると、途中で面倒になって離脱されるおそれがあります。
「年齢や勤め先など商品配送に不要な項目まで入力させられる」「アンケートに回答しないと購入手続きを完了できない」といったサイトは、ユーザーから不信感や不満を抱かれる可能性が高く、カゴ落ちが発生しやすくなるため注意が必要です。
購入のためにアカウントの登録が必要だった
商品を購入するためにアカウントの登録を必須としているECサイトも多いでしょう。しかし、これもカゴ落ちの原因になります。商品を選択し、いざ購入しようと思ったのにアカウント作成を促されると、面倒に感じる人も少なくありません。
「色々なサイトに個人情報を登録するのが不安」「すでに多数のサイトでアカウントを作っていて、新しいアカウントをなるべく増やしたくない」といったユーザーもいます。このような人は、購入画面でアカウントの登録を促されるとサイトを離脱してしまう可能性が高いと考えられます。
配送に予想以上に時間がかかる
買い物カゴを表示して配送予定日を確認したとき、ユーザーの予想よりも日数がかかるとカゴ落ちのリスクが高まります。一般的に、ユーザーはなるべく早く商品を手にしたいと思っているので、「すぐに発送されないなら別のECサイトで買おう」と考える人も多いでしょう。
ECサイトにおいて配送までの時間は利便性を大きく左右する要素のため、商品価格やサイトの使いやすさなどと同様に意識すべきポイントのひとつです。
サイト自体やセキュリティに不安を感じた
ECサイトで買い物をするには、住所や氏名、クレジットカード番号などを入力しなければなりません。これらの情報は流出すると不正利用の被害にあうおそれがあるため、信頼性の高いサイトでなければ入力をためらう人がほとんどでしょう。
そのため、サイト自体やセキュリティに不安を感じると購入手続きを進めるのが怖くなり、商品を購入しないまま離脱してしまう原因になります。例えばサイトの完成度が低いと、正規のECサイトかどうか不安になってしまう人もいるでしょう。
支払い方法の選択肢が少ない
支払い方法の選択肢が少なく、ユーザーが希望する支払い方法を選択できないのも、カゴ落ちが起きる原因のひとつです。近年はQRコード決済や後払い決済など、クレジットカード以外の支払い方法を日常的に利用しているユーザーも多くいます。
世の中には数多くのECサイトがあり、豊富な支払い方法を用意しているサイトも少なくありません。そのため、希望の支払い方法が使えないと、ほかのサイトで購入しようと離脱してしまう原因になります。
購入や決済のタイミングでエラーが発生した
ECサイトの動作が不安定で、購入や決済のタイミングでエラーが発生すると、ユーザーはそのサイトを利用することに不安や面倒さを感じてしまいます。例えば、購入時にエラーが起きて買い物カゴがリセットされると、ユーザーは商品をもう一度買い物カゴに入れなければなりません。
また、決済時にエラーが起きると「決済が完了したかどうかわからない」「再度手続きをすると二重請求されるかもしれない」などの不安を感じさせてしまいます。エラーが多いとカゴ落ちどころか二度とサイトを利用してもらえなくなる可能性もあるため、対策が必要です。
返品ポリシーに不安や不満がある
ECサイトは商品が届くまで現物を確認できないため、返品ポリシーに納得できなければ購入しないというユーザーもいます。一方、企業側は返品の発生を防ぎたいと考えているので、「開封後の返品は不可」「返品時の送料はユーザー負担」など、企業に有利な返品ポリシーとなっているケースも見られます。
このような返品ポリシーはユーザー側のリスクが大きく、「もし商品を返品したくなったら困る」と感じて購入をためらう原因になるため、注意しましょう。
そもそも買うつもりがなかった
人によっては「少し気になったから」「あとで詳細を確認しようと思った」といった理由で買い物カゴに入れる場合もあります。このようなケースはそもそも購買意欲があまり高くなく、カゴに入れたまま忘れてしまっている人もいるでしょう。この場合、商品のPRやクーポンの配布などアプローチ次第では購入につなげられる可能性があります。
カゴ落ちを防ぐ9つの対策
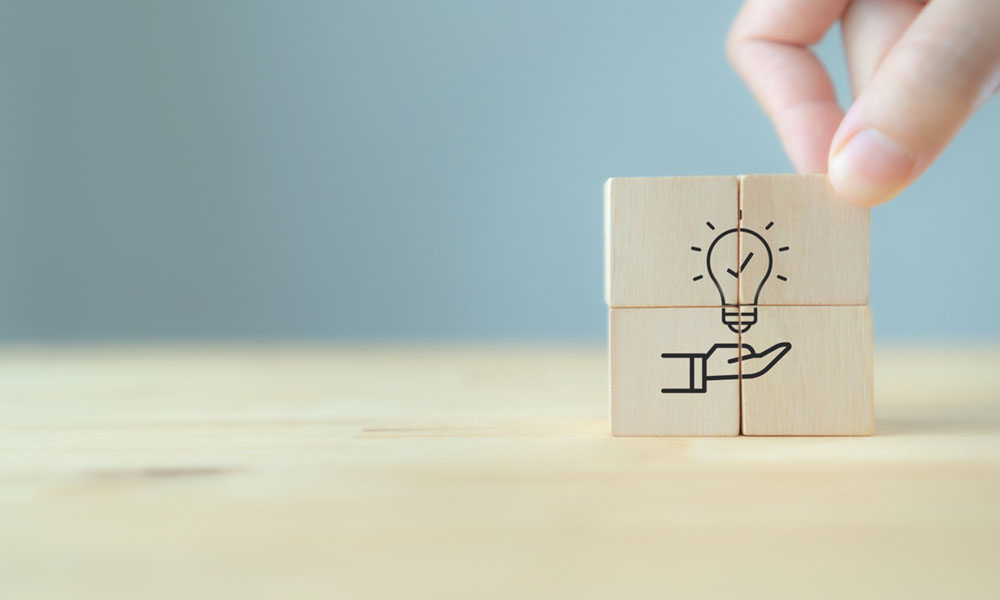
ここまで紹介してきたとおり、カゴ落ちが発生する原因はさまざまです。そのため、カゴ落ち対策の手段も多岐にわたります。なるべく多くの対策を実施することでカゴ落ちのリスクを下げられるので、まずはどのような対策があるのか把握しておきましょう。
カゴ落ちを防ぐための9つの方法を紹介しますので、自社のECサイトに取り入れられるものがないかチェックしてみてください。
送料や手数料を下げる
ユーザーに「想定より高い」と感じさせないためには、送料や手数料を下げる、もしくは無料にするという方法があります。送料や手数料がかからなければ、商品ページで確認した金額以上の費用は発生せず、違和感なく購入まで進んでもらえます。
しかし、送料や手数料を下げるのは困難なケースも多いでしょう。その場合は、商品ページにも送料や手数料を明記しておくと効果的です。商品選択中からトータル費用を意識できるため、買い物カゴを見たときに「思ったより高い」と感じさせずに済みます。
会員登録不要で購入できるようにする
ECサイトでの購入時にアカウントの登録を必須としている場合、会員登録不要で購入できるようにするとカゴ落ち率を下げられる可能性があります。買い物カゴで配送と決済に必要な情報を入力するだけで購入できる状態なら、「会員登録が面倒」「これ以上アカウントを増やしたくない」というユーザーも抵抗なく買い物ができるでしょう。
何らかの理由で会員登録が必要な場合は、登録の手続きをなるべく簡素化するのがおすすめです。例えば、購入時に入力した住所などの情報をそのままアカウント作成に用いて、購入と会員登録を一度に完了させるなど、ユーザーの手間を最小限に抑える工夫をしましょう。
合計金額はリアルタイムで確認できるようにする
買い物カゴを表示しなくても合計金額がわかるようになっていれば、ユーザーは常に合計金額を意識しながら買い物ができます。「想定より高い」と感じさせることなく、スムーズに決済まで進んでもらえるでしょう。
合計金額以外にも、カートの中に入っている点数や商品を確認できるとより親切です。ユーザーにとって利便性の高いECサイトだと感じてもらえれば、リピーターになってもらえる可能性もあります。
ショップやサイトの安全性を伝える
ユーザーに安心して買い物をしてもらえるように、ECサイトの運営会社やセキュリティ対策の内容などを明記するようにしてください。公開している情報が少なすぎると、詐欺サイトだと疑われてしまう可能性があります。
運営会社が明確になっていて、セキュリティ対策をしっかり実施しているECサイトなら、個人情報を入力するときの抵抗感が薄れます。商品の発送や決済には住所や氏名、クレジットカード番号などが必要になるため、ユーザーがこれらを安心して入力できるサイトにすることが大切です。
サイトの表示スピード改善やサーバー強化をおこなう
サイトの利用中にエラーが出るとユーザーが不安を感じて離脱の原因となるため、エラーの原因を特定してサーバー強化などの対策を行いましょう。エラーが出ずサイトをスムーズに利用できるようになれば、カゴ落ちのリスクを軽減できます。
エラーだけでなく、サイトの表示スピードにも注意してください。エラーにならなくても、ページの表示に時間がかかるとユーザーがストレスを感じます。サイトが重い・固まるといった事象が出ていないか確認し、必要に応じて表示スピードの改善にも取り組みましょう。
返品ポリシーを明確にする
返品ポリシーがカゴ落ちの原因になっているケースもあるため、まずは返品ポリシーがわかりやすいところに表示されているか確認が必要です。返品ポリシーの内容が不明確だと、不安で購入に踏み切れない人もいます。
返品ポリシーを商品ページなどわかりやすいところに明記している場合は、内容が企業に有利なものになっていないか確認してください。ユーザー側の負担が大きい返品ポリシーでは、購入のハードルが上がってしまいます。
カゴ落ちのリスクを考慮すると、返品ポリシーを厳しくして返品を防ぐのではなく、アフターフォローなど別の側面から返品対策を行い、返品ポリシー自体はユーザー目線を意識した内容のほうがよいでしょう。
支払い方法の選択肢を増やす
QRコード決済や電子マネー、キャリア決済や後払い決済など、支払い方法は多種多様です。また、QRコード決済ならPayPayやLINE Pay、電子マネーならSuicaや楽天Edyなど、それぞれの支払い方法の中にもさまざまなブランドがあります。
人によって日常的に利用している支払い方法やブランドは異なるため、幅広いニーズに応えられるよう支払い方法の選択肢を増やしましょう。さまざまな種類の支払い方法に対応していると、ユーザーの離脱を防ぐだけでなく他のECサイトとの差別化や競争力の強化にもつながります。
配送オプションを増やす
「配送までに時間がかかる」という理由でのカゴ落ちを防ぐには、配送オプションを増やすのが効果的です。例えば、すぐに商品を届けてほしいユーザーのための「特急オプション」を用意したり、複数の配送方法から選べるようにしたりすると、より細かいユーザーニーズに対応できます。
また、荷物を受け取れるタイミングは人それぞれなので、配送日や時間帯をユーザーが選べるようにするのもよいでしょう。
カゴ落ちをリマインドする
「商品を買い物カゴに入れたまま忘れている」というケースもあるため、買い物カゴに残っている商品があることをユーザーにリマインドするのもカゴ落ち対策のひとつです。メールやアプリのプッシュ通知でリマインドすると、購入に進んでくれる可能性があります。
リマインドをする際にクーポンの配布や新商品のお知らせなどを盛り込むと、ECサイトに再訪問してくれる可能性が高まります。もしカゴ落ちしている商品が不要になったり、別のサイトですでに購入してしまったりしている場合でも、自社のECサイトに誘導できれば別の商品の購入につながるかもしれません。
関連記事:【例文付き】リマインドメールとは?活用例と書くときのポイント
カゴ落ちのリマインドにはSMSがおすすめ

メールやプッシュ通知などカゴ落ちをリマインドする手段はいくつかありますが、特におすすめなのはSMSです。SMSは携帯電話番号宛てにメッセージを送信できるサービスで、近年では企業から顧客への連絡に用いるケースも増えています。
SMSの大きなメリットは、開封率と到達率の高さです。SMSを送受信するためのアプリはスマートフォンに標準搭載されていて、特別な設定をしていない限りSMSを受信するとポップアップ通知が出るようになっています。そのためSMSが届いたことに気づきやすく、メールと比較して開封率が高いのが特徴です。
電話番号はメールアドレスと比較して変更の頻度が少なく、長期間同じ電話番号を使い続けている人も少なくありません。そのため連絡手段として長く活用でき、到達率が高いという特徴もあります。
リマインドを送ってもユーザーに見てもらえなければ意味がないため、カゴ落ちのリマインドにはユーザーに届きやすく見てもらいやすいSMSを活用しましょう。
関連記事:【SMS活用編】第7回リマインド通知としてのSMS活用。再配達率抑制にも貢献
SMSによるカゴ落ちのリマインド例
ここでは、「カートに商品が残っていることをリマインドする」と「他のおすすめ商品を案内する」という2つのケースで使えるSMSの例文をそれぞれ紹介します。リマインドの参考にしてください。
【カートに商品が残っていることをリマインドする場合】
カートに残ったままの商品がありますが、お買い忘れはございませんか?
下記URLより、ご購入手続きを完了させることができます。
※すでにご購入済みの場合は、ご了承ください。
https://〜
【他のおすすめ商品を案内する場合】
お客様がチェックされた商品をもとに、おすすめの商品をご案内します。
詳細は、下記URLよりご確認いただけます。
https://〜
カゴ落ちをSMSで回避しよう
カゴ落ちはECサイトの買い物カゴに商品を入れたものの購入されずに放置されている状態のことで、ECサイトを運営するうえで避けては通れない課題です。
本記事で紹介したとおり、カゴ落ちにはさまざまな原因があります。自社のECサイトに該当するものがないかチェックして、カゴ落ち対策に取り組みましょう。
カゴ落ち対策としてリマインドを送信するなら、SMSの活用がおすすめです。NTTコム オンラインが提供する「空電プッシュ」は国内シェアNo.1のSMS送信サービスで、さまざまな業界でリマインドやプロモーションに活用されています。ユーザーへのアプローチにSMSを活用したいと考えている方は、「空電プッシュ」をぜひご検討ください。