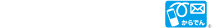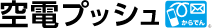医療業界において患者との連絡が必要な業務は多々ありますが、電話やメール、郵送物で患者・利用者との連絡を取ろうとするものの、なかなか確認いただけないという課題があります。繰り返し連絡をしなければならず、大きな業務負荷になっているケースも少なくありません。
とくに2024年4月から医師に対する時間外・休日労働上限規制が開始されることからも、さまざまな業務を効率化する必要に迫られている医療機関も多いのではないでしょうか。
本記事では、医療業界(病院・診療所・デイサービス・薬局等)が患者や利用者とのコミュニケーションにおける課題に対して、医療業界ならではのSMSの利点、そして、どのようにSMSを有効活用されているかを事例とあわせてご紹介します。
- 医療業界における患者との電話やメール、郵送物でのやりとりは、なかなか確認してもらえないことが多い
- 2024年4月医師に対する時間外・休日労働時間の上限規制が開始されるため、業務を効率化する必要がある
- 医療機関の業務効率化には、SMSを活用することがおすすめ
- SMSは診療予約忘れや診察待ちの患者様の呼び出し、災害時の職員への安否確認などのさまざまな課題の解決策となる
目次
- 2024年4月から時間外・休日労働上限規制がスタート
- 医療業界ならではのSMSの利点
- SMSの活用シーン1:診療予約忘れ防止の確認や定期健診の案内
- SMSの活用シーン2:予約完了の連絡
- SMSの活用シーン3:診察待ちの患者様の呼び出し
- SMSの活用シーン4:福祉・介護施設での利用者家族との連絡
- SMSの活用シーン5:調剤薬局での服薬フォロー連絡
- SMSの活用シーン6:災害時の職員への安否確認
- 医療業界でのSMS活用事例
- 医療業界でSMSを有効活用しよう

2024年4月から時間外・休日労働上限規制がスタート
2024年4月1日から、医師に対する時間外・休日労働時間の上限規制がスタートします。これにより基本的に医師の年間の時間外・休日労働時間の上限は、一般の労働者と同程度の960時間とされます。
これは政府が主導する「医師の働き方改革」の一環であり、2021年5月に公布された「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」に基づいています。この改革は医師の長時間労働や休日確保が難しいことを解決するための施策です。
しかし、実際は医師不足や高齢化による医療介護へのニーズの増加といった問題は解決されていません。今後規制により医師の勤務時間がこれまでよりも減少すれば、問題が大きくなる可能性もあるでしょう。そのため、医療機関における業務効率化が喫緊の課題となっています。
医療業界ならではのSMSの利点

医療業界の業務を効率化するための方法の1つとして、SMS(ショートメッセージサービス)の活用が挙げられます。SMSの利点について詳しく見ていきましょう。
着眼率・開封率が高い
さまざまな業務連絡を行う際に、メールの場合は受信ボックスでたくさんのメールに埋もれてしまい、なかなか開封してもらえないことがあります。一方でSMSは、メールほど使用頻度が高くないため、ほかのメッセージに埋もれて気づかないということが少ない傾向にあります。また、受信時にはポップアップ通知が行われるため、受信者の目に留まりやすいことも特徴です。確実に読んでもらいたいメッセージを届ける方法として、SMSは非常に効果的といえるでしょう。
携帯電話番号だけで繋がる
SMSは相手の携帯電話番号宛てにメッセージを送信します。一般的に携帯電話番号は変更される機会が少ないため、到達率が高くなります。一方でメールはアドレスが変更されたり、郵送は相手が引越しなどを行うと住所が変更されたりして、届かなくなることも多いでしょう。
さらに、電話番号はそのままで使用するキャリアを変更できるナンバーポータビリティ制度の利用も広がっており、今後さらに携帯電話番号を変更する人は少なくなるでしょう。SMSを活用することで、メッセージの到達率を高められます。
利用者のアプリのインストールが不要
SMSの機能はほとんどの携帯電話に標準で搭載されています。専用のアプリをインストールしたり、細かな設定をしたりしなくても、すぐに利用できることがメリットです。アプリのインストールや設定が必要な場合、携帯電話の操作に慣れていない方であれば、難しく感じることも多いでしょう。また、実際にメッセージを受信した際も、タップのみで簡単に確認できます。難しい操作は不要で直感的に使用できるため、誰でも簡単にメッセージの送受信が行えます。
ガラケーでも利用できる
LINEなどのメッセージアプリは、スマホでの利用が基本で、ガラケーでは利用できないことが多いです。しかし、SMSはガラケーでも利用できます。高齢者が多い医療業界においては「ガラケーでもSMSは届く」という特長はメール等の連絡手段と比較して、非常に大きな利点であるといえます。
高齢者のガラケー所有率は60代で19%、70台で26%(※)と決して少なくない割合です。また、ガラケーの廃止時期はキャリアによって異なり、auは2022年3月31日、ソフトバンクは2024年1月下旬、ドコモに至っては最長で2026年3月31日とまだまだ利用される見込みです。医療業界で万人に連絡を取るための手段を選ぶ際に、ガラケー対応はまだまだ無視できない状況にあるというのが現状であり、それがSMSを選ぶ理由の一つになりえます。
(※出典: NTTドコモ モバイル社会研究所)
SMS送信サービスの利用で一斉送信が可能
SMS送信サービスを利用すると、一斉配信や予約配信を行うこともできます。こうした機能を活用すれば、予約の確認やリマインドの作業に費やしていたリソースを効率化することが可能です。人件費も削減できるため、コストカットも実現できるでしょう。
また、SMS送信サービスはシステム連携のためのAPIを各種用意しています。医療業界向けのソリューションサービスとのシステム連携を比較的容易に実装することができるため、さまざまな業務の自動化を図ることも可能です。
関連記事:SMSを一斉送信するには?メリットとサービスの選び方を紹介
SMSの活用シーン1:診療予約忘れ防止の確認や定期健診の案内

課題
期間が空いた受診日の予約忘れや人間ドック・健康診断や定期健診の連絡を、電話や郵送で行っても、「電話に出てもらえない」「郵便物を見てもらえない」「折り返し連絡が来ない」などの課題が散見されました。
解決策
SMSを活用し診療予約日時のリマインダー連絡、人間ドックや健康診断の日程連絡、便検査等の事前準備のリマインド、歯科定期健診の定期的な連絡を知らせることで、予約忘れ防止や定期健診の受診率アップ、健康診断の満足度向上に繋げることができます。
【例文】
https://~
SMSの活用シーン2:予約完了の連絡
課題
Web予約システムで診療予約を受け付ける場合、患者が予約した日程を忘れてしまうケースがよく見られます。患者が予約日をメモし忘れていると、予約日を確認したいという問い合わせが発生し、受付スタッフの負担につながります。
解決策
予約完了時にSMSで予約日時を記載した案内を送信することで、患者はいつでも簡単に予約内容を確認できます。これにより、予約忘れを防ぐことが可能です。また、メッセージ内に変更やキャンセルの方法も記載しておけば、患者とのやりとりがスムーズになり、受付スタッフの負担軽減にもつながります。
【例文】
日時:〇月〇日(〇曜日)午後3時
場所:〇〇クリニック(住所)
ご都合が悪い場合は、以下のリンクから変更やキャンセルをお願いします。
https://~
SMSの活用シーン3:診察待ちの患者様の呼び出し
課題
医療機関受診時、診察までの待ち時間が長いことから、患者様から「いつ順番が回ってくるのか」という問い合わせは多くあります。また、診察を待つための待合スペースが混雑することも、感染症予防などの観点で改善したいポイントです。しかし、順番が回ってきたことを通知するシステムがない場合、カフェなどの外部でゆっくり待っていただくこともできません。
解決策
SMSを活用すると、診察の順番が近づいたタイミングでメッセージを送り、患者様を呼び出すことができます。これにより患者様は医療機関外で診察待ちができるようになり、結果的に待合スペースの混雑が緩和され、密を避けることにつながります。
患者様は混雑した空間で待つ必要がなくなるため、ストレスが軽減されるでしょう。また医療機関の職員への問い合わせも減るため、医療機関の業務効率化にもつながります。医療機関と患者様の双方にメリットのある解決策です。
【例文】
XXX-XXXX-XXXX
SMSの活用シーン4:福祉・介護施設での利用者家族との連絡
課題
老人ホームやデイサービス利用者の急な体調の変化や施設での様子を伝えるなど、介護職員から利用者のご家族とコミュニケーションが発生する場面は多々あります。電話をかけてもなかなか繋がらない、通話時間が長くなってしまい介護職員・ご家族の双方の負担になるといった課題も顕在化しています。
また、こうした入居者の状況をメールで通知するシステムを提供されているシステムベンダーでも、メールを見ていただけない等の課題があるのではないかと考えます。
解決策
SMSを利用して、その日のご家族の様子を伝えたり、また緊急で連絡をしても電話に出ていただけなかった際にメモとしてSMSを送ることにより、コミュニケーションの負担軽減に繋がります。また、メール通知をSMSに切り替えることで、開封率があがり、ご家族に施設利用者の状況をしっかり理解いただけることは施設にとっても大きなメリットになります。
【例文】
XXX-XXXX-XXXX
SMSの活用シーン5:調剤薬局での服薬フォロー連絡
課題
2020年9月から改正医薬品医療機器等法による「服薬フォロー」の義務化が始まりました。オンラインによる服薬指導も必要に応じて認められたものの、テレビ電話等では負担が大きく、メールでの伝達もメールアドレス取得率が低い、郵送は届くまでに時間がかかるなど、課題がありました。
解決策
携帯電話番号のみでメッセージを送ることができるSMSを活用することで、患者に適切な服薬フォローが効率的に可能になります。調剤の管理システムとSMS送信サービスをAPI連携することで管理画面から情報を入力・送信でき、調剤の受付・完了通知などのリマインダーへの利用拡大にも繋がります。
【例文】
XXX-XXXX-XXXX
SMSの活用シーン6:災害時の職員への安否確認
課題
地震や台風、洪水などの災害が発生した際に、医療機関では迅速に職員の安否確認と勤務ができる状態であるかの確認を行わなければなりません。被災者の救護活動や緊急医療サービスを提供する必要があるからです。しかし、災害発生時には電話が集中してつながらない可能性が高く、インターネット接続も不安定であるため、職員となかなか連絡が取れないことが課題となります。また安否情報を効率的に収集できない場合、情報の混乱や遅延が生じる可能性もあります。
解決策
SMSは一般的に災害時でも電話よりつながりやすく、職員との連絡を取れる可能性が高くなります。災害時には電話やメールではなくSMSを活用することで、迅速な安否確認と勤務可否の状態を把握できるでしょう。職員の数が多く、1人1人確認する作業が大変な場合は、SMS送信サービスとアンケートフォームなどを活用することで効率的に安否確認を実施できます。
【例文】
https://~
医療業界でのSMS活用事例

実際に医療業界においてSMSを活用して業務効率化と患者様の満足度をアップさせた事例を紹介します。
国内最多の病床数を有する藤田医科大学病院には、1日平均2,500~2,600人の患者様が訪れます。これだけ多くの患者様が訪れることで、どうしても診察までの長い待ち時間が発生してしまっていました。待合スペースは混雑し、順番が回ってきたことを知らせるシステムがなかったため、患者様に病院の外でゆっくり待っていただくこともできません。
そこで同病院は、診察の順番が近くなったら患者さんに通知するシステムを導入するために、NTTコム オンラインが提供するSMS送信サービス「空電プッシュ」を選択しました。SMSなら、専用デバイスが不要のためコストがかからず、アプリをダウンロードする手間もないため簡単です。さまざまな患者様がストレスなくスムーズに使えることが決め手でした。
導入後は病院外のカフェなどで待つことが可能になり、待合スペースの混雑が緩和され職員に対する問い合わせも減少しました。業務の効率化に成功し、患者様の満足度の向上にも貢献しています。
医療業界でSMSを有効活用しよう
ここまでご紹介したように患者や施設利用者とのコミュニケーションが発生するさまざまな業務でSMS活用が可能です。NTTコム オンラインでは、100%に近い開封率を誇るSMSを利用して、携帯電話番号のみで一斉・個別にメッセージを送信できるSMS送信サービス「空電プッシュ」を提供しています。高いセキュリティを維持しながら、SMSを一斉に配信できることから、従来の連絡手段(電話、郵便物、Eメール)に代わる新たなツールとしてご活用頂いています。
ご紹介した診療予約忘れ防止や定期健診案内、介護利用者のご家族との連絡、薬の副作用情報の提供、診察待ちの患者様の呼び出し、災害時の職員への安否確認などの課題をお持ちのご担当者様はぜひ、着眼率の高いSMSをご検討ください。