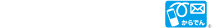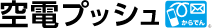特定電子メール法は、迷惑メールの防止を目的に定められた法律です。広告・宣伝のためにメールを活用している企業は、特定電子メール法について必ず理解しておく必要があります。違反すると罰則を受ける可能性があるため、禁止事項やルールをしっかり把握しておきましょう。
本記事では、特定電子メール法の概要と、違反しないために押さえておくべきポイント・注意点を解説します。SMSにもこの法律は適用されるため、メールだけでなくSMSを活用している場合もチェックしておいてください。
目次
- 特定電子メール法は迷惑メールの送信を規制する法律
- 特定電子メール法が施行された背景
- 特定電子メール法に違反するとどうなる?罰則の内容
- 特定電子メール法のポイント
- SMSも特定電子メール法の対象
- メール・SMSを活用する際は特定電子メール法に注意

特定電子メール法は迷惑メールの送信を規制する法律
特定電子メール法は広告や宣伝を目的とするメールを対象とした法律で、正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といいます。迷惑メールの防止を目的として、2002年に施行されました。
その後、対象範囲の見直しや状況に応じた規制の強化など複数の法改正が行われ、現在の特定電子メール法となっています。2008年の改正で、後ほど詳しく紹介する「オプトイン規制」などが盛り込まれました。
特定電子メール法が施行された背景

特定電子メール法が施行された背景として、迷惑メールの増加が挙げられます。インターネットが普及して電子メールが広く使われるようになったことで、2001年頃から迷惑メールが急増しました。
迷惑メールは受信者の許可を得ずに不特定多数に送信され、広告や宣伝だけでなく詐欺のような内容のものもあります。メールを受け取った人がトラブルに巻き込まれるケースもあり、社会問題となったことから、法律による規制が求められるようになりました。
その結果施行されたのが、特定電子メール法です。法律が施行され罰則もあることから、迷惑メールの抑止に役立っています。
特定電子メール法に違反するとどうなる?罰則の内容
特定電子メール法では「あらかじめ同意を得ていない人への配信」「送信者情報を記載せずに配信する」などを禁止しています。これらの禁止事項やルールに違反した場合、総務大臣および内閣総理大臣から業務の改善命令や停止命令が出されます。
改善命令・停止命令が出されているのにも関わらずこれに従わない場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課されるため、注意が必要です。また、法人に関しては行為者を罰するほか、罰金が「3000万円以下」とされています。
特定電子メール法に違反するようなメールは、受信者に迷惑メールとみなされる可能性が高いでしょう。これは罰則があるだけでなく、企業のイメージダウンにつながるのも大きなデメリットです。
広告・宣伝のためにメールを送信しているのに相手からの印象が悪くなってしまっては逆効果のため、法律は必ず守るようにしてください。
特定電子メール法のポイント

特定電子メール法を理解するうえで押さえておきたいのが、次の3つのポイントです。
- オプトイン規制
- 送信者の表示義務
- なりすまし禁止
上記3つのポイントについて、詳しく解説します。
オプトイン規制
1つ目のポイントは「オプトイン規制」です。「オプトイン規制」とは、簡単に言うと「同意を得ていない人に対しては広告・宣伝メールを送信してはいけない」というルールです。オプトイン規制について、以下で詳しくみていきましょう。
オプトインとは
オプトインとは、広告・宣伝メールの配信に対して事前に許可を得ることです。英語で「Opt In」と表記し、「選択」という意味を持ちます。特定電子メール法ではこのオプトインを義務付けていて、メールアドレスの保有者の同意なく広告・宣伝メールを配信してはいけません。例えば、名簿業者から購入したリストをメルマガの配信に利用するのは禁止です。
事前承諾の取り方はさまざまですが、会員登録のフォームや商品購入ページなどに、メールの配信に関して同意を求めるチェックボックスを設置しているケースがよく見られます。オプトイン規制には例外があり、インターネット上に公開されているメールアドレスや、直接名刺交換をした相手に対しては、事前の承諾なしに広告・宣伝メールを送信しても違法にはなりません。
オプトアウトも重要
オプトインだけでなく、オプトアウトも重要です。オプトアウトとは、広告・宣伝メールの受け取りを受信者が拒否することです。英語で「Opt Out」と表記し、「脱退」などの意味を持ちます。
広告・宣伝メールを送信する場合、受信者がいつでも拒否できるように配信停止の意思表示ができる仕組みを用意しておかなければなりません。配信停止の依頼ができない状態で広告・宣伝メールを送信すると、特定電子メール法違反となります。
もちろん、配信停止の依頼があったのに広告・宣伝メールを送信し続けるのも違反です。また、配信停止の方法がわかりにくいメールも迷惑メールとみなされる可能性があるため、配信停止の申込みフォームはわかりやすい箇所に表示しましょう。
同意を証明する記録の保存
オプトインに関しては、事前に同意を得るだけでなく「同意を得た」と証明する記録を保存しておくことも大切です。記録がなければ、なにかトラブルになったときにオプトイン規制を守っていることを証明できません。
メールアドレスごとに、同意を得た方法や日時などを記録して保存しておきましょう。保存期間は、広告・宣伝メールの配信を停止してから1ヶ月と定められています。
ただし、なんらかの違反があって措置命令を受けた場合は、保存期間が異なるため注意してください。命令を受けてから1年以内に広告・宣伝メールを送信した場合は、送信日から1年間はオプトインの証明を保存しておく必要があります。
送信者の表示義務
特定電子メール法では、広告・宣伝メールに送信者の情報を明記するよう定めています。具体的には、以下の項目の表示が必要です。
- 送信者の氏名・名称
- 送信者の住所
- 苦情や問い合わせの窓口
- 配信停止ができる旨と配信停止依頼の送信先・URL
送信者がわからないメールは相手に不信感を与えてしまうため、上記の項目はメール本文のわかりやすい場所に明記するようにしてください。
なりすまし禁止
送信元のなりすましも、特定電子メール法で禁止しています。送信元のメールアドレスを偽ったり、送信元がわからないように加工したりした状態でメールを配信してはいけません。
広告・宣伝メールを配信する際は、送信元のメールアドレスが相手から確認できる状態になっている必要があります。
SMSも特定電子メール法の対象

特定電子メール法は、メールだけでなく、携帯電話番号宛てに送信するSMSも対象になります。近年、ビジネスにSMSを活用する企業が増えているため、SMSで広告・宣伝を行う場合にも特定電子メール法に違反しないよう注意してください。オプトインやオプトアウト、送信者の表示義務など、メールと同様の対応が必要です。
ただし、あくまでも広告・宣伝を目的としている場合に限ります。SMSは本人認証や利用料金の督促、サービス提供のリマインダーなど、宣伝以外にもさまざまな用途で活用されています。広告・宣伝目的でない場合は、特定電子メール法の対象外です。
関連記事:【第4回】SMS導入担当者が必ず理解しておきたい3つの法律
メール・SMSを活用する際は特定電子メール法に注意
広告・宣伝にメールやSMSを活用する際には、特定電子メール法について理解しておきましょう。事前の許可なくメールを配信したり、配信停止の仕組みを用意していなかったりすると法律違反となり、悪質だと判断されると最悪の場合懲役や罰金が課される可能性があります。
「知らず知らずの間に特定電子メール法に違反していた」ということのないよう、法律の内容についてしっかり把握しておかなければなりません。
近年、メールだけでなくSMSを活用する企業が増えています。SMSをビジネスに活用するなら、NTTコム オンラインが提供する「空電プッシュ」がおすすめです。
国内シェアNo.1の法人向けSMS送信サービスで、業界を問わず多くの企業で活用されています。到達率の高さなどメールにはないメリットも多いため、この機会にぜひご検討ください。