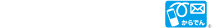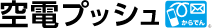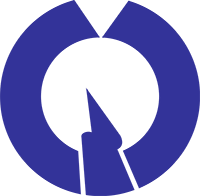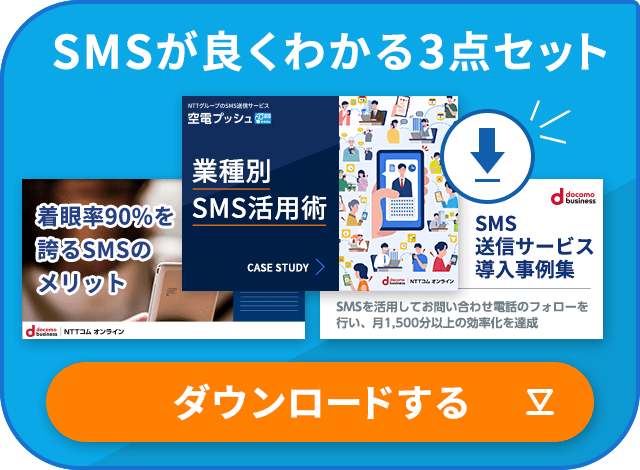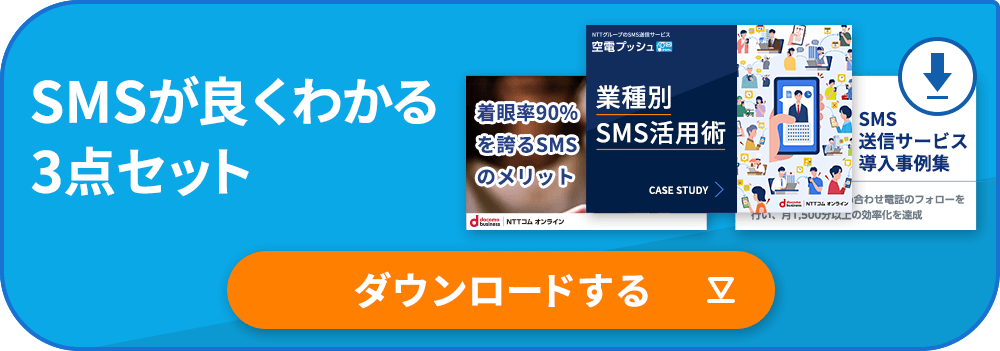督促状送付後のリマインドにSMSを活用
送信後10日以内に約500万円の納付を実現
- 督促状に反応がない滞納者に電話催告を行っていたが、メッセージを伝えられるのは40%程度と行き詰まっていた
- 電話催告は業務にあたる職員の時間的負担が大きく、代替手段を探していた
- 電話催告をSMSでのリマインド送信に変更したことで、職員の時間的負担が軽減
- SMSを受け取った方のうちの2割強から、税金の納付や折り返しの連絡など、市に対してのアクションがあった
- SMS送信後10日間での納付金額約500万円を実現
東京都の多摩地区西部に位置する福生市。都心まで1 時間以内でアクセスでき、市内には、多摩川や玉川上水、緑の多い公園がたくさんある「子育てしやすい街」として知られています。そんな同市が市税の催告業務に役立てるために、2020年7月に導入したのが「空電プッシュ for LGWAN」です。同市の市民部収納課収納係の川村氏に、導入の経緯や活用における工夫点などについてお伺いしました。

電話での催告は約40%の住民にしか伝えられず、対象者にメッセージを伝える新たな手段を模索
はじめに川村様が所属する部署の役割と担当業務について教えてください。
川村氏:福生市の市民部収納課収納係で係長を務めています。住民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料などのいわゆる「市税等」の徴収業務を行う部署で、業務には、二重納付をされた方などへの還付手続きや、期日までに納付いただけるようにする納税啓発活動なども含みます。そして、納期限までに納付がなかった場合に発生する、督促状の送付や催告、最終的には財産の差し押さえに至ることもある「滞納整理」の業務も担っています。
職員は、会計年度任用職員(非正規雇用)の方も含めて20名ほどいます。事務的な作業は役割分担していますが、市民から納付のご相談を窓口や電話で受けたり、滞納者へ電話で催告を行ったりする業務は、課の全員であたっています。
どのような課題があって、SMS送信サービスの導入を検討されたのでしょうか?
川村氏:収納課では、年間で約3万〜4万通の督促状を発行しています。それだけではお支払いいただけない滞納者に対して納付を促す催告は、以前から電話や書面、訪問で行っていました。そのなかで、特に納期限が過ぎて間もないタイミングでの電話催告は効果が高いことが明らかになっていました。そこで福生市では、滞納から早い段階での電話催告を、市税の収納率向上を図るための主要な対策と位置付け、重点的に実施しています。
電話催告は、電話で直接相手の方と会話してお支払いをお願いすることで効果が得られ、その効果も高いのですが、一件ずつ手作業で電話をかける必要があるため、時間がかかってしまうという課題がありました。電話をかけても不在だったり、何かしらの理由で電話をとってもらえなかったり、繋がらないことが多く、過去の実績では電話をかけた回数に対し、ご本人・ご家族等や留守番電話への伝言も含めて、メッセージを伝えられたのは40%程度という結果でした。
この課題を解決するために、電話催告に変わる手段を検討しはじめました。当初候補としてあがったのは、自動音声による電話催告システムです。電話をかける作業を自動化することで効率化は図れるのですが、当市には日本語が通じない外国人の市民も多いので、機械的な音声だけで催告するのは難しいだろうと判断し、見送りました。
他にも、派遣や業務委託を活用したコールセンター方式も検討しました。自動音声と違い、柔軟な対応が期待できますが、人口5万人ほどの当市には大きすぎる出費となるため、費用対効果という点で導入には至りませんでした。
そんななか、注目したのが、SMS送信サービスです。テキストで臨機応変にメッセージを送信できる点や、SMSの着眼率が高い点に魅力を感じ、導入に向けて具体的に動き始めることになりました。
LGWANに対応し、誤送信防止機能が標準で備わっている安心感が導入の決め手に
他社の類似サービスもあるなかで、空電プッシュに決定された理由はどのようなところにありましたか。
川村氏:空電プッシュについては、自治体向けの展示会でデモを体験したことがあり「これならよさそうだ」という感触がありました。他社サービスとも比較検討しましたが、空電プッシュはLGWANに対応していること、送信先である携帯電話番号の契約者が変わったことを検知してSMS送信を自動で止める誤送信防止機能が標準で備わっていることが、導入の決め手となりました。
導入はどのような段取りで進めて行かれましたか? ご苦労や工夫されたことがありましたら教えてください。
川村氏:空電プッシュの導入を決めてから、実際に運用が始まるまで、2年かかりました。というのも、市役所内部で承認を得る際に「市からSMSを送信するサービスをはじめると、これを悪用した特殊詐欺が増えるのではないか」という指摘に対し、反証できるだけの運用方法や対策の検討が不足していたこともあり、当初は導入が見送られてしまったのです。
そこで、市消費者相談室の相談員の方に相談し、特殊詐欺の実情や、それを防ぐ手立てについて、具体的なアドバイスを受けました。それを参考に、特殊詐欺に悪用されづらいメッセージの運用ルールをまとめ、次の年に再度提案を行った結果、無事、事業化に向けた承認を得ることができました。
SMS導入でメッセージの到達率が88.2%に。SMS送信後10日以内に約500万円の納付を達成
現在の空電プッシュの具体的な活用方法について教えてください。
川村氏:ひとつは、督促状や催告書を郵送してから一定期間後に、改めて納付を促すリマインドとしてSMSを活用しています。具体的には「収納課から郵送した書類を確認してほしい」というメッセージをお送りしています。
もうひとつは、個々の担当者が「この方には市役所にきてほしい」という場合に、「収納課から大切なお知らせがあるので窓口まできてほしい」という内容をSMSで送信しています。
いずれの場合も、個人情報保護の観点から、万一、無関係な人に送られてしまっても問題ないように、メッセージには氏名、滞納や未納という言葉を含めないようにしています。また、特殊詐欺防止の観点から、電話番号やURLも記載しないようにしています。
空電プッシュ導入後、どのような効果がありましたか?
川村氏:電話催告では1件に5分として、仮に100名に催告を行うと500分ほどかかることになります。さらに、お電話がつながるとお話が長くなってしまう場合もあり、職員の時間的な負担が大きくなっていました。空電プッシュを導入してからは、SMSを送信したあとは、折り返しの電話や来庁があったタイミングで対応を行えばよいので、職員の時間的負担が軽くなりました。
また、SMS導入後も引き続き電話や書面、訪問も並行して行っていますが、電話の到達率が40%程度なのに対し、SMSの着信率は88.2%と圧倒的に、こちらからのメッセージを届けることができています。さらにSMSを受け取った方の2割強が、その後、税金の納付や折り返しの連絡など、何らかのアクションを起こしていることがわかりました。
SMS導入の効果を図るために、SMS送信後10日間での納付金額を調べたところ、1年目は約200万円、2年目は約500万円の納付がありました。これは、十分な成果が得られていると思います。
そのほかにも運用面での変化や効果がありましたら教えてください。
川村氏:SMSを受け取って来た市民の方からは、「電話があっても仕事中は折り返せない。郵便物も確認できておらず、SMSを受け取ってはじめて未納に気がついた」という反応がありました。これまで電話や郵送では反応がなかった層にリーチできている実感があります。
また、外国人の方に対しては、外国語のメッセージを送ることができます。そして、日本語のメッセージであっても、SMSは画面に文字が残るため、日本語がわかる人に見てもらって内容を理解するなど、SMSをきっかけに自主的に連絡をしてもらえるケースも増えています。
最後に、今後の空電プッシュの活用や展望を教えてください。
川村氏:現在、滞納者で分割でのお支払いをお約束された方で、納付期限が過ぎてしまった方に対してのご連絡は郵送や電話で行っていますが、今後は郵送代や電話にかかる時間を圧縮するため、「お約束の期限が過ぎています」とお支払いを促す内容のSMSに変更することも検討しています。
また、当市は外国人の方の比率も多いため、空電プッシュのシステム内で翻訳ができるとより分かりやすくお伝えすることができるのではないかと考えています。
他の事例を見る